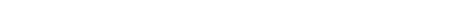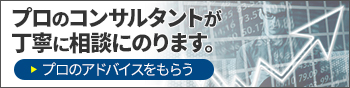2025/08/20
現代において、企業の評判はインターネットの検索結果やSNSの投稿によって一瞬で形成されます。
たった一つのデマや悪意のある投稿が、長年築き上げてきたブランドの信頼を一瞬で崩壊させ、ビジネスの存続そのものを脅かすリスクがあることをご存知でしょうか?
Webマーケティングにおいて、風評被害は単なる「悪い噂」ではなく、企業の死活問題です。
オンライン上の評判をいかに管理するかが、今や企業の命運を分けると言っても過言ではありません。
風評被害が引き起こされることで以下のようなリスクが発生する可能性があります。
・ブランドイメージの毀損
ユーザーは検索エンジンやSNSで情報を得るため、ネガティブな情報が上位に表示されたり拡散されたりすると、ブランドに対する信頼が失われ、企業の価値が低下します。
・売上の減少
購買意思決定の過程で口コミや評判を参考にする消費者が多いため、風評被害は直接的な売上減少につながります。
・採用活動への悪影響
企業の悪い評判は、求職者にも影響を与え、優秀な人材の獲得が困難になります。
・事業継続性のリスク
風評被害が深刻化すると、取引先との関係悪化や株価の下落など、事業そのものが立ち行かなくなる恐れがあります。
今回は、風評被害が企業にとってどんなリスクがあるのか風評被害を受けたらどのような対応を行った方が良いのかなどについて、ご紹介します。
起こりうる風評被害の具体例
Web上で起こりうる風評被害は多岐にわたります。
たった一つの情報が、大きな被害につながるケースを具体的に見ていきましょう。
・根拠のないデマや虚偽情報
事実に基づかない「あの店の料理は使い回しだ」「この製品には有害物質が含まれている」といった噂が、SNSや匿名掲示板で拡散されるケースです。
信憑性がなくても、多くの目に触れることで事実のように扱われてしまいます。
・悪意のある誹謗中傷
競合他社や、企業に個人的な恨みを持つ人物による、意図的なネガティブキャンペーンや誹謗中傷です。
個人のアカウントを装って不満を書き込むなど、巧妙な手口でブランドイメージを傷つけようとします。
・従業員の不適切行為
従業員がプライベートでSNSに不適切な投稿をしたり、勤務中に不謹慎な行動をとったりした動画が拡散され、企業全体のモラルが問われる炎上案件です。
個人の行動が、企業全体の信頼を損なうリスクがあります。
・過去の不祥事の再燃
既に解決したはずの過去の問題が、何らかのきっかけで再び掘り起こされ、インターネット上で炎上するケースです。
デジタルタトゥーとして過去の情報が残り続けるため、いつ再燃するか分かりません。
・サービスや製品の不具合
製品の欠陥やサービスの不具合に対して、ユーザーの不満がオンライン上で一斉に噴出し、ネガティブな口コミが連鎖的に広がるパターンです。
一つの不満が、やがて「あの会社の製品は欠陥品だ」というレッテルにつながります。
・サジェスト汚染
検索エンジンの検索窓に企業名を入れた際に「〇〇 詐欺」「〇〇 倒産」といったネガティブなキーワードが自動表示される現象です。
これは、実際にそのキーワードで検索しているユーザーが多いことを示しており、風評被害の典型例と言えます。
風評被害が発生しやすいメディア
風評被害は、その内容によって拡散されやすいメディアが異なります。
メディアごとの特徴とリスクを理解しておくことが、効果的な対策を立てる上で重要です。
■SNS(Twitter、Facebookなど)
情報が瞬時に、爆発的に拡散される為、一度炎上すると手がつけられなくなるケースが多いです。
リツイートやシェアによって、企業の公式な発言が切り取られたり、意図しない形で広まったりするリスクもあります。
■匿名掲示板・口コミサイト(5ちゃんねる、転職会議、食べログなど)
匿名性が高く、誰でも自由に書き込める為、悪意のある誹謗中傷や虚偽情報が生まれやすい場所です。
信憑性が低いとされていても、検索結果に表示されることで、潜在的な顧客の目に留まるリスクがあります。
■ブログ・個人サイト
専門家やインフルエンサーの影響力が強い場合があり、彼らが発信するネガティブな情報が信頼性を伴って拡散されるリスクがあります。
また、過去のブログ記事が検索結果に残り続け、風評被害の火種となることもあります。
■ニュースサイト・まとめサイト
公式な情報として扱われやすい為、一度ネガティブな記事が出ると、その信頼性を覆すのが非常に困難になります。
まとめサイトは、特定の情報を恣意的に切り取って拡散する為、意図しない形で炎上が拡大する原因となります。
風評被害の対策方法
風評被害への対策は、予防と発生後の対応の二段階で考えることが重要です。
1. 予防策(発生前)
■ソーシャルリスニングの実施
風評被害の兆候を早期に発見するためには、インターネット上の情報を常時監視する「ソーシャルリスニング」が不可欠です。
・無料ツール
GoogleアラートやTweetDeckなどを活用し、自社名や商品名、経営者名などのキーワードを設定して、新しい情報が投稿された際に通知を受け取ります。
・有料ツール
専門のソーシャルリスニングツールを導入すれば、SNSだけでなく、匿名掲示板やブログ、口コミサイトまで網羅的に監視できます。
ネガティブな感情を含む投稿を自動で検知し、アラート通知を送る機能も備わっています。
■ポジティブな情報の発信
公式サイト、ブログ、SNSなどを活用し、日頃から企業の価値や製品の品質に関する信頼できる情報を発信し続けます。
これにより、検索結果を良質なコンテンツで埋めることができます。
■レビュー管理と顧客対応
良いレビューを増やす仕組みを作り、ネガティブなレビューには迅速かつ誠実に対応することで、顧客満足度を高めます。
2. 対応策(発生後)
■迅速な事実確認と初動対応
炎上や風評被害が発生したら、まずは事実関係を正確に把握します。
そして、公式な見解をできるだけ早く発表し、デマには毅然とした態度で反論し、問題があった場合には速やかに謝罪します。
■検索エンジンの最適化(SEO)
・逆SEO
ネガティブなサジェストを押し下げるために、ポジティブなコンテンツを大量に作成し、検索結果の上位を占めることを目指します。
これにより、ネガティブなキーワードがサジェストに表示されにくくなる効果が期待できます。
・広告の活用
検索広告を活用し、ネガティブなキーワードで検索された際に、公式見解のページを上位に表示させる方法も有効です。
■法的な対応と削除依頼
・法律専門家への相談
悪質なデマや誹謗中傷に対しては、弁護士に相談し、投稿の削除依頼や法的措置を検討します。
・検索エンジンへの削除依頼
名誉毀損やプライバシー侵害など、法令に違反する情報については、GoogleやYahoo!などの検索エンジンに直接削除を依頼することもできます。
ただし、これは検索結果から表示を消すだけで、元の情報は残る点に注意が必要です。
また、サジェスト汚染についても、同様に検索エンジンに削除依頼を行うことが可能です。
FAQ(よくある質問)
Q1. 風評被害対策はどのくらいの頻度で行うべきですか?
A1. 風評被害はいつ、どこで発生するか予測できません。
その為、日常的な監視(ソーシャルリスニング)が最も重要です。
新しい情報が投稿された際にすぐに検知できるよう、Googleアラートなどの無料ツールや、専門の有料ツールを活用して、常に自社ブランドや関連キーワードをモニタリングしましょう。
Q2. 炎上してしまった場合、SNSの投稿はすぐに削除するべきですか?
A2. 状況によります。安易な削除は「都合の悪い情報を隠蔽した」と捉えられ、かえって炎上を拡大させるリスクがあります。
まずは事実関係を正確に把握し、削除する前に公式な見解を発表することが重要です。
虚偽や明らかな誹謗中傷であれば削除依頼を検討しますが、単なる不満の声であれば真摯に受け止め、丁寧に対応する方が信頼回復につながることが多いです。
Q3. 本人が風評被害だと思っていなくても、実際は風評被害という例はありますか?
A3. はい、あります。
例えば、企業の公式アカウント担当者が、個人的な意見として特定の社会問題について発言したとします。
担当者自身は「個人的な発信」だと思っていても、世間はそれを「企業の公式見解」と見なすことが少なくありません。
結果として、意図しない形で炎上し、企業のブランドイメージが傷つくことがあります。
他にも、従業員がSNSで自社製品の不満を投稿した場合、本人は個人的な感想のつもりでも、外部からは「会社の人間が欠陥を認めている」と解釈され、大きな風評被害につながる可能性があります。
Q4. サジェスト汚染は自社で対策できますか?専門業者に依頼するべきですか?
A4. 基本的な対策(ポジティブな情報の発信など)は自社で行えますが、サジェスト汚染の根本的な解決は難易度が高いです。
特に、ネガティブなキーワードが頻繁に表示される場合や、複数のキーワードにわたる場合は、専門業者に依頼することを推奨します。
専門業者は、検索エンジンのアルゴリズムを熟知しており、効率的な逆SEOや、法的な手段を組み合わせた対応を期待できます。
参考記事:サジェスト汚染の消し方・削除方法とは?風評被害・ネガティブワード対策をしよう
Q5. 弁護士に相談する場合、費用はどのくらいかかりますか?
A5. 弁護士費用はケースによって大きく異なります。
相談料は30分〜1時間で5,000円〜1万円程度が一般的ですが、初回相談を無料としている事務所も多いです。
投稿の削除依頼や発信者情報開示請求を行う場合は、着手金や成功報酬が発生します。
まずは複数の弁護士事務所に相談し、見積もりを取ることをお勧めします。
まとめ
今回は、風評被害がもたらす企業へのリスクについて、ご紹介しました。
Webマーケティングにおける風評被害は、企業のブランド、売上、採用活動に深刻な影響を与える「死活問題」です。
しかし、適切な対策を講じることで、そのリスクを最小限に抑えることが可能です。
本記事で解説したポイントをまとめると、以下のようになります。
■風評被害は多岐にわたる
デマや誹謗中傷、従業員の不適切行為など、様々な形で発生し、サジェスト汚染もその典型例です。
■メディアごとの特性を理解する
SNS、匿名掲示板、ニュースサイトなど、それぞれのメディアで異なるリスクがあるため、適切な監視が必要です。
■予防と対応の二段構えで臨む
・予防
ソーシャルリスニングで兆候を早期に発見し、日頃からポジティブな情報発信でブランドを強化する。
・対応
炎上発生後は迅速に事実確認を行い、逆SEOや法的対応を検討する。
風評被害は「いつか起こるかもしれない」ではなく、「いつ起きてもおかしくない」リスクです。
まずは、自社ブランドのオンライン上の評判を定期的にモニタリングすることから始め、万が一に備える体制を構築しましょう。
弊社BOPコミュニケーションズでは、Web広告の配信・運用を承っております。
・売上を伸ばすためにWeb広告を活用してみたい。
・自社で広告配信をしているが、手探り状態なので効率を上げたい。
・広告の運用をプロに任せて、よりビジネスを大きくしていきたい。
そんな場合は、お気軽にご相談ください!
★フォームからすぐにお問い合わせしたい場合はこちら↓