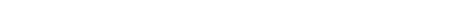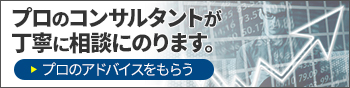2025/05/12
SEO対策に関わる方であれば、ホワイトハットSEO・ブラックハットSEOという言葉を聞いたことがある方も多いかと思います。
しかしその中間的な存在として「グレーハットSEO」という手法も存在します。
今回は、グレーハットSEOとは何か、なぜ企業がグレーハットSEO使うのか、そしてグレーハットSEOのリスクとメリットなどについてご紹介します。
グレーハットSEOとは?
グレーハットSEO(Gray Hat SEO)とは、検索エンジンのガイドラインには完全には違反していないものの、その意図や手法が不自然・操作的と判断される可能性があるSEO対策のことを指します。
ホワイトハットSEOが「検索エンジンとユーザーの両方にとって価値あるコンテンツを正攻法で提供する」アプローチであるのに対し、グレーハットSEOは「正攻法とブラックハットの間を突く手法」ともいえます。
代表的なグレーハットSEOの手法
グレーハットとされる主な手法には、以下のようなものがあります。
1. 中古ドメインの活用
過去に運用されていたドメインを購入し、そのドメインパワーを活かして検索順位を上げる手法です。
→ 過去の運用履歴が良質であれば問題ありませんが、評価だけを目的とした活用はグレー扱いに。
2. 自作自演リンクの設置
複数の関連サイトを作成して、相互リンクや一方向リンクを張ることで被リンク数を増やす施策です。
→ コンテンツの質よりもリンク操作に重きを置くと、ガイドライン違反に近づきます。
3. 記事スピニング
AIやツールを使って他サイトの文章を「リライト風」に改変し、オリジナルコンテンツのように見せる方法です。
→ 検索エンジンは重複コンテンツや品質の低いコンテンツを評価しません。
4. 過剰な内部リンクやキーワードの埋め込み
ユーザーにとっては不要な場所にリンクやキーワードを埋め込み、検索評価を不自然に上げようとする施策です。
→ ユーザー体験を損なう場合、評価が下がる要因になります。
中古ドメインを使った被リンク施策はグレーハットSEO?
グレーハットSEOの代表的な手法として、「中古ドメインの活用による被リンク対策」が挙げられます。
これは、過去に高い評価を受けていたドメインを取得し、自社サイトへの被リンクを意図的に設置することで、検索順位の向上を狙うものです。
一見、効果的に思えるこの施策ですが、Googleのガイドラインでは「検索順位操作を目的としたリンク構築」はリンクスキーム(不正行為)として警告対象となっています。
その為、このような手法はホワイトハットとは言えず、グレーハットSEOに分類されます。
■グレーハットSEOに該当する中古ドメインの使い方の例
・被リンク目的でのみ運用される、コンテンツの薄い中古ドメイン
・明らかに関連性のないサイトからのリンクばかりを集めている
・過去の被リンク評価だけを狙って中古ドメインを使う
これらの手法は、短期的に順位が上がる可能性もありますが、Googleのアルゴリズム更新や手動ペナルティの対象となるリスクを孕んでいます。
一方で、自然に残っていた中古ドメインからリンクされること自体は問題ありません。
あくまで、リンクの質と背景、そしてユーザーにとっての価値があるかどうかが評価の基準となります。
なぜ企業がグレーハットSEOに手を出してしまうのか?
SEOは中長期的な成果が求められる施策です。
しかし現場では以下のような事情から、つい「グレーな手法」に傾いてしまうケースがあります。
・短期間で成果を求められる(特にスタートアップや新規事業)
・広告費削減のため、早くオーガニック集客を軌道に乗せたい
・SEO外注先から「裏技的」な提案を受けた
・ライバルが検索上位にいて焦りを感じる
こうした背景があると、少しでも効果の出やすい方法に手を出したくなるのが人間の心理です。
しかし、グレーハットSEOは一時的に成果が出ても、それが長続きしないどころかリスクになることもあるので、グレーハットSEOには注意が必要です。
グレーハットSEOを活用しがちな企業の特徴
グレーハットSEOは、検索エンジンのガイドラインには明確に違反していないものの、リスクが伴う手法です。
では、なぜこのような中間的な施策を選ぶ企業があるのでしょうか?その背景には、以下のような事情が関係しています。
・中小企業・スタートアップ
→ 広告費をかけずに短期間で集客したいため、多少のリスクを取る傾向がある。
・期間限定キャンペーンを行う企業
→ キャンペーン期間中に一時的でも検索順位を上げたいという狙いがある。
・海外市場向けの戦略をとる企業
→ 海外では検索アルゴリズムが緩く、グレー施策が通用する地域もある。
・SEO代行会社の提案を鵜呑みにしてしまう企業
→ 知識が不十分なまま、短期成果を優先して危うい手法を導入するケースがある。
グレーハットSEOのリスクとデメリット:検索エンジンからのペナルティとは?
グレーハットSEOは、現時点ではガイドライン違反と明言されていなくても、将来的に違反とされる可能性があります。
Googleは定期的にアルゴリズムをアップデートしており、過去に通用した手法が突然ブラックリスト入りすることも。
代表的なペナルティの種類
・検索順位の大幅な下落
・インデックス削除(Googleから存在が見えなくなる)
・手動ペナルティ(Search Consoleで通知)
・一度ペナルティを受けると、回復には数カ月単位の時間とリソースが必要になります。
その為、企業にとっては、大きな信用損失に繋がる可能性があります。
ホワイトハットSEOとグレーハットSEOの違い
SEO施策を検討する際、ホワイトハットとグレーハットの違いを理解しておくことは極めて重要です。
両者には、長期的な信頼性や施策の安全性に大きな差があります。
■ホワイトハットSEO
・Googleのガイドラインに沿った正攻法
・ユーザー満足度を最優先にしたコンテンツ作り
・効果が安定しやすく、ペナルティのリスクがほぼない
・中長期的な資産として積み上がる
■グレーハットSEO
・ガイドラインの“隙間”を突いたややリスキーな手法
・一時的な順位上昇を狙えるが、効果が不安定
・アルゴリズムの変更によりペナルティを受けるリスクがある
・長期的にはサイトの信頼性を損なう可能性も
企業として安定した集客とブランド価値の向上を目指すなら、中長期的に評価されるホワイトハットSEOが王道です。
グレーハットSEOは「短期成果を狙う賭け」として理解し、慎重に判断すべきです。
よくある質問(FAQ)
Q. グレーハットSEOを使っていても、ペナルティを受けなければ問題ないのでは?
A. 現時点で問題がなくても、将来的なGoogleのアルゴリズム更新で手法が違反認定される可能性があります。長期的にはリスクが高いため、慎重な判断が必要です。
Q. 中古ドメインを使うだけでペナルティになるのですか?
A. 中古ドメインの活用自体は違反ではありませんが、「評価操作の目的」で使われるとグレーハット〜ブラックハットとみなされることがあります。
Q. どうしてSEO会社がグレーな手法を使うのですか?
A. 短期的な成果を強調しやすいため、クライアント獲得や契約維持を目的にリスクの高い施策を提案するケースがあります。信頼できる業者かどうか見極めが必要です。
まとめ
今回は、グレーハットSEOについて、ご紹介しました。
グレーハットSEOは一見魅力的に見えるかもしれませんが、企業のブランド価値や中長期的な集客を考えると、慎重に判断すべき領域です。
SEOは「地道で誠実な改善」が最終的な勝者になります。
Web担当者としては、表面的なテクニックに惑わされず、ユーザー目線と検索エンジンの意図に沿ったコンテンツ戦略を選択することが重要です。
弊社BOPコミュニケーションズでは、Web広告の配信・運用を承っております。
・売上を伸ばすためにWeb広告を活用してみたい。
・自社で広告配信をしているが、手探り状態なので効率を上げたい。
・広告の運用をプロに任せて、よりビジネスを大きくしていきたい。
そんな場合は、お気軽にご相談ください!
★フォームからすぐにお問い合わせしたい場合はこちら↓