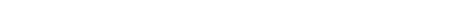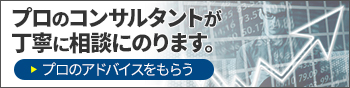2025/05/15
業務改善やマーケティングの現場で、いま注目されているのが「CAPDo(キャップドゥー)」というフレームワークです。
従来のPDCAサイクルに代わる形で導入され始めており、特に変化の激しいビジネス環境において高く評価されています。
今回は、CAPDoの特徴や活用シーン、PDCAとの違いについて、ご紹介します。
CAPDoとは?
CAPDoは、次の4つのステップで構成される改善サイクルです。
Check(現状の把握)
まず、現場や顧客、市場の「いま」を観察し、客観的に分析します。数字や行動、発言などのデータをもとに現状を把握します。
Act(仮説立案)
Checkで得られた情報を踏まえ、「なぜそのような状態になっているのか」「何を改善すべきか」という仮説を立てます。
Plan(計画)
仮説に基づいて、具体的な施策やアクションプランを策定します。
Do(実行)
計画を実行し、結果をまた次のCheckに生かします。
ポイントは、「最初に計画(Plan)を立てる」のではなく、「まず現状(Check)を観察する」ところから始まる点です。
なぜPDCAでは不十分なのか?
PDCAサイクルは、Plan(計画)からスタートする為、「そもそも現状がよくわからない」「課題が曖昧」という状況には不向きです。
とりあえず計画を立ててみても、それが現実に即していなければ、Do(実行)で成果が出にくく、Checkの段階でようやく問題が明らかになるという構造的な弱点があります。
一方、CAPDoは最初にCheckから始める為、「課題が何か」を明確にしたうえで進めることができます。
つまり、CAPDoは問題の“発見力”が高いのです。
どんなときにCAPDoが役立つのか?
特にCAPDoが力を発揮するのは、次のような状況です。
・新しい商品やサービスの立ち上げ時
・顧客のニーズや行動がよく見えていないとき
・競合環境や市場が変化しているとき
・なぜ成果が出ないのか、原因がはっきりしないとき
こうした状況では、机上の計画よりも、まず現場を観察して事実をつかむことが重要です。
CAPDoのCheck → Act → Planという順番は、まさにこの考え方にフィットしています。
マーケティング現場でのCAPDo活用例
マーケティングにおいてもCAPDoは非常に有効です。
例えば、ペルソナ設計を行う場合、従来は「30代女性・主婦層」といった仮想の顧客像を立てて進めがちですが、それが実態とズレていれば、どんな施策も的外れになります。
CAPDoではまず、アクセス解析、購入履歴、SNSの反応などをもとに現実の顧客像を観察(Check)し、そこから「本当に響く顧客は誰か?」という仮説を立て(Act)、施策を設計(Plan)します。
このプロセスによって、机上では見えてこない顧客インサイトが浮き彫りになり、施策の効果も高まります。
マーケティング戦略立案におけるCAPDoの応用例
CAPDoは、マーケティング戦略を立てる際にも非常に有効です。
特に、顧客のニーズが多様化し、過去の成功パターンが通用しなくなっている現代においては、「Check(現状把握)」から始める思考が重要になっています。
以下に、具体的な応用例をいくつか紹介します。
1. 商品のターゲット設定
従来のPDCAでは、まず「30代女性向け」などと計画し、広告やキャンペーンを展開するケースが多く見られました。
しかし、実際の購買データやSNSでの反応を見ると、購入しているのは「20代の感度の高い層」だった、ということも少なくありません。
CAPDoでは、まず実際のアクセスデータや口コミ、売上の傾向を観察(Check)し、そこから「実際にこの商品を求めているのは誰か?」という仮説を立て(Act)、それに合わせたターゲティングと訴求内容を設計(Plan)するという流れになります。
このように、理想ではなく“現実”に合った戦略が構築できる点が、CAPDoの強みです。
2. 新商品の市場投入戦略
新商品を立ち上げる際、「Plan→Do」から始めてしまうと、市場ニーズとズレた商品が完成してしまい、苦戦するリスクが高くなります。
CAPDoでは、最初に競合商品や市場のトレンド、既存顧客の声などを分析して「どのような課題が未解決なのか?」を見極め(Check)、そのうえで自社商品が提供すべき価値の方向性を仮説立て(Act)します。
そこから、ターゲット市場、チャネル、価格戦略、メッセージの内容などを計画(Plan)し、テストマーケティングや限定リリースなどで実行(Do)します。
この手順により、顧客とのズレを最小限に抑えた市場投入が可能になります。
3. 広告・コンテンツ施策の改善
広告やオウンドメディアの改善でも、CAPDoの発想は役立ちます。
例えば、ある記事が想定ほど読まれていない、ある広告がクリック率が低いという問題があったとします。
PDCA型のアプローチでは、先に「このタイトルを変えてみよう」といった対症療法的なPlanを立てがちですが、CAPDoではまず「なぜ読まれていないのか?」「どの部分で離脱されているのか?」というデータの観察から始めます(Check)。
そこから「情報の出し方が不親切」「検索ニーズとのズレがある」といった仮説(Act)を立て、改善施策(Plan)を設計し、テスト的に実行(Do)します。
このプロセスによって、感覚や思い込みではなく、根拠に基づいたコンテンツ改善が可能になります。
業種別のCAPDoマーケティング活用例
◆ BtoB(SaaS企業)
シナリオ:リード獲得が伸び悩んでいる
Check(現状把握)
過去3ヶ月のLP(ランディングページ)流入データやCVR(コンバージョン率)を分析。
→「トラフィックはあるが、フォーム入力前での離脱が多い」ことが発覚。
Act(仮説立案)
「フォームの項目が多く、ハードルが高いのではないか」「導入メリットが伝わっていないのでは」と仮説を立てる。
Plan(計画)
① フォームを2ステップに分割して離脱率を下げる
② 成功事例を上部に配置し、導入効果を先に訴求する構成へ
Do(実行)
修正後LPを公開し、改善前後でCVRを比較。効果を次のCheckに反映。
◆ ECサイト(アパレルブランド)
シナリオ:売上が横ばいで成長が鈍化している
Check
アクセス解析から、訪問数は増えているのに購入率が下がっていることを確認。SNSのコメントから「サイズ感がわかりにくい」「モデル画像と実物の印象が違う」といった不満が見えてきた。
Act
「購入の意思決定に必要な情報が不足している」という仮説を立てる。
Plan
① 商品ごとにサイズ比較モデルを3名配置
② 動画で着用感を伝えるコンテンツを導入
③ LINEでサイズ相談ができるチャット導線を追加
Do
主要商品でテスト導入し、平均購入率の変化を計測。
◆ 飲食店(チェーン展開)
シナリオ:新メニューの来店誘導が弱い
Check
Googleビジネスプロフィールの閲覧数や口コミを分析。「インスタで見たけど近所にあると知らなかった」との声が複数確認される。
Act
「視覚的訴求は成功しているが、店舗認知が低く“行動”に結びついていない」という仮説を立てる。
Plan
① 投稿に店舗一覧マップを付ける
② SNS広告に「○○駅徒歩5分」といった地名訴求を追加
③ Googleマップ上の画像・投稿を最新に更新
Do
1ヶ月間、地域別に配信。来店数とクーポン利用回数を追跡。
◆ 教育業(オンライン講座)
シナリオ:無料体験から本申込みへの転換率が低い
Check
体験参加者のアンケートで、「良かったが本申込みを迷っている」「比較している講座がある」という回答が多数。競合講座のLPと比較したところ、価格・サポート体制の説明が薄いことが判明。
Act
「コンテンツの良さは伝わっているが、申込みの“決め手”が弱い」という仮説を立てる。
Plan
① 本申込み者の声を「迷っていた理由→申込んだ決め手」というストーリー形式で掲載
② 無料体験参加者限定の特典を用意
③ 競合比較表を導入し、強みを明示
Do
改善LPを配信し、体験→本申込み率をモニタリング。
データドリブンな時代にマッチしたフレームワーク
現代のビジネスでは、GoogleアナリティクスやCRM、SNS分析など、Checkの材料となるデータが豊富にあります。
CAPDoは、こうした情報を活用する前提で設計されている為、データドリブンな改善活動にもぴったりです。
また、組織全体で「事実を見る文化」「仮説から考える文化」を醸成するうえでも、CAPDoは有効です。
CAPDoでPDCAは不要になるのか?
CAPDoの登場によって「PDCAはもう古い」「使えない」と思われがちですが、実際はそうではありません。
CAPDoはPDCAを否定するものではなく、目的や環境によって「より適した方法」を選ぶべきだという発想から生まれたものです。
PDCAは安定的な業務改善において依然として非常に有効です。
一方、CAPDoは不確実性が高く、仮説検証をスピーディに行いたい現場やマーケティングに向いています。
つまり、CAPDoはPDCAの「進化系」ではあっても、「上位互換」ではありません。
状況に応じて両者を使い分けることが、現代のビジネスでは求められているのです。
PDCAとCAPDoは使い分けが重要
CAPDoがあるからといって、PDCAが不要になるわけではありません。
例えば、広告の運用改善やLPのA/Bテストといったすでに構造が決まっている業務では、PDCAのほうがスムーズに改善を回せます。
一方で、課題が曖昧だったり、そもそも正解が見えないような場面では、CAPDoのほうが柔軟で、効果的な打ち手が見つかりやすくなります。
まとめ
今回は、CAPDoについて、ご紹介しました。
CAPDoは、現場や顧客の“今”を見ることから始める改善サイクルです。
変化が激しく、先の見通しが立ちづらい現代においては、机上の計画よりも、まず事実を見てから考えるほうが成果につながりやすくなっています。
PDCAとCAPDo、どちらが優れているというよりも、目的や状況に応じて柔軟に使い分けることが、現代ビジネスの正解といえるでしょう。
弊社BOPコミュニケーションズでは、Web広告の配信・運用を承っております。
・売上を伸ばすためにWeb広告を活用してみたい。
・自社で広告配信をしているが、手探り状態なので効率を上げたい。
・広告の運用をプロに任せて、よりビジネスを大きくしていきたい。
そんな場合は、お気軽にご相談ください!
★フォームからすぐにお問い合わせしたい場合はこちら↓