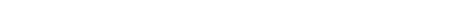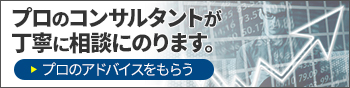2025/10/30
「このデザイン、今っぽくないですよね。」
クライアントからそう言われた経験はありませんか?
あるいは逆に、最新トレンドを取り入れたデザインを提案したところ、「うちのブランドに合わない」と却下されたことはないでしょうか?
WEBデザイナーにとって、トレンドとの付き合い方は永遠のテーマです!
2025年現在、ニューモーフィズム、グラスモーフィズム、3Dイラスト、大胆なタイポグラフィ、ダークモード、AIで生成されたビジュアルなど、次々と新しい表現手法が登場しています。
私自身、駆け出しの頃は「トレンドを取り入れれば良いデザインになる」と単純に考えていました。
海外の最新デザインサイトを毎日チェックし、見つけた表現をそのまま自分のデザインに適用していました!
しかし、ある日クライアントから厳しいフィードバックを受けました。「デザインは確かにかっこいい。でも、うちの顧客層にこれは響かない。あなたは誰のためにデザインしているんですか?」
その言葉にハッとしました。私はクライアントのビジネス目的やターゲットユーザーを無視して、自分が「かっこいい」と思うトレンドを押し付けていたんです!
トレンドを知ることはめちゃくちゃ重要です!
しかし、それ以上に重要なのは、そのトレンドを「使うべきか、使わないべきか」を判断する力です。
この判断力こそが、デザイナーとしての真の実力を示すものだと私は考えています。
という事で今回は、デザイントレンドとの正しい向き合い方と、クライアントの目的に合わせた取捨選択の方法について、実践的な視点から解説していきます!
初心者デザイナーの方は、何度も見返せるようにブックマークがオススメです!
なぜデザイントレンドを追う必要があるのか?
まず前提として、トレンドを知らないことはデザイナーにとって致命的だと私は思っています!
◎デザイントレンドは時代を映す鏡
デザイントレンドは、単なる流行ではありません!
その時代のテクノロジー、文化、ユーザーの価値観を反映したものです。
例えば、フラットデザインが主流になった背景には、モバイルデバイスの普及とレスポンシブデザインの必要性がありました。立体的なスキューモーフィズムは美しいけど、小さな画面では視認性が低く、データも重い。だからシンプルなフラットデザインが求められたんです。
現在のトレンドである「ダークモード」は、長時間スマホを見るユーザーの目の疲労を軽減するという実用的な理由がありますよね!
AIで生成されたビジュアルの台頭は、制作コストの削減と表現の多様性を両立する時代のニーズを表しています。
つまり、トレンドを知ることは、「今、ユーザーが何を求めているか」「どんな技術が可能になったか」を知ることなんです!私はこれを「時代の空気を読む力」だと考えています。
デザイントレンドを知らないことで起きる3つの問題
1. 時代遅れのデザインになる
トレンドを全く無視したデザインは、ユーザーに「古い」「更新されていない」という印象を与えます。特にWEBサイトは、企業の顔です。古臭いデザインは、企業自体が時代に取り残されているという印象につながりかねないので注意してください!
私が以前見たあるコーポレートサイトは、2000年代のFlashサイトのような過度な装飾と複雑なナビゲーションで、訪問者を困惑させていました。これは明らかに機会損失です…。
2. クライアントとの会話ができない
クライアントが「競合サイトのようなモダンな感じにしたい」と言ったとき、最新のデザイントレンドを知らなければ、その「モダン」が何を指しているのか理解できません。
逆に、トレンドを理解していれば、「それはグラスモーフィズムという手法ですね。御社のブランドイメージとマッチするか検討しましょう」と専門家として会話を深められます!
3. 選択肢の引き出しが少なくなる
デザインは選択の連続です。
トレンドを知らないということは、選択肢を自ら狭めているという事と同じです。
引き出しが多いほど、様々な課題に対して最適な解決策を提案できますよね!
私は、トレンドを「使うための知識」ではなく、「選択肢を増やすための知識」として考えています。知っていて使わない選択をするのと、知らないから使えないのでは、天と地ほどの差があるんです。
トレンド情報の効率的な収集方法
では、どうやってトレンドをキャッチアップすればいいのか。私が実践していた方法を紹介します。
◎デザインギャラリーサイトの定期チェック
Awwwards・Behance・Pinterest(WEB Design, UI Designなどのボード等)・Dribbble
私は毎朝通勤の電車で、これらのサイトを眺めていました。
「いいね」をするだけでなく、「なぜこのデザインが評価されているのか」を考えることが非常に重要です!
◎SNSでデザイナーをフォローする事!
X(旧Twitter)やInstagramで、海外の著名デザイナーや、日本の第一線で活躍するデザイナーをフォローしていますか?
彼らの発信から、単なる視覚的トレンドだけでなく、デザイン思想やプロセスも学べるんです!
◎デザイン系メディアの購読
「WIRED」「FastCompany」などのテック・デザインメディアは、なぜそのトレンドが生まれたのかという背景まで解説してくれます!表面的な見た目だけでなく、思想を理解することが、後述する「使うべきかの判断」につながります。
ただし、ここで注意したいのは、「トレンドを追うこと」が目的になってはいけないということです!
あくまで知識として蓄積し、必要なときに引き出せる状態にしておく。それが理想的なトレンドとの距離感だと私は考えています。
トレンドに流されることの危険性
トレンドを知ることは重要ですが、それに盲目的に従うことは、デザイナーとしての思考停止になるので注意してください!
◎「トレンド=正解」ではない
多くの若手デザイナーが陥る罠が、「流行っているから良いデザイン」という思い込みです。
しかし、デザインの良し悪しは、目的を達成できるかどうかで決まります。
私が以前担当した地方の老舗和菓子店のWEBサイトリニューアルでは、最初、グラデーションを使った現代的でポップなデザインを提案しました。確かに見た目は今風でした。しかし、クライアントの反応は微妙でした…。
「うちの和菓子は、100年続く伝統製法で作っています。この軽やかなデザインは、その重みを伝えられないと思います」
その言葉で目が覚めました!トレンドを追うあまり、和菓子店の「伝統」「格式」「職人の技」という本質的な価値を無視していたんです。
結局、余白を多く取り、明朝体をベースにした落ち着いたデザインに変更しました。トレンドからは外れているかもしれませんが、ブランドの本質を正確に伝えるデザインになり、クライアントも大変満足してくれました!
この経験から学んだのは、「トレンド」と「ブランドの本質」が一致しないときは、迷わず本質を優先すべきだということです!覚えておいてください。
トレンドに流されることで起きる4つの問題
1. ブランドアイデンティティの喪失
すべての企業が同じトレンドを採用すれば、すべてのWEBサイトが似たような見た目になります。これは差別化の観点から致命的ですよね!
実際、2020年頃、多くのスタートアップ企業がグラデーションとイラストを使った似たようなデザインのサイトを作り、「スタートアップっぽいけど、どの会社も同じに見える」という問題が起きました。
2. ターゲットユーザーとのミスマッチ
若年層向けのトレンドを、高齢者向けサービスに適用すれば、ユーザーは混乱します。逆もまた然りです。
私が昔見たBtoB企業のサイトでは、過度に奇抜なデザインが、「信頼性に欠ける」という印象を与えていました。BtoBの意思決定者は、奇抜さよりも安定性と実績を求めます。デザインはそれに合わせるべきだったんです。
3. 機能性の犠牲
見た目の美しさを追求するあまり、使いやすさが損なわれることがあります。
例えば、ニューモーフィズム(柔らかい影で立体感を表現する手法)は美しいですが、コントラストが低く、視認性に問題があります。アクセシビリティを考えると、多くの場面で不適切な表現になります!
私は、「美しいが使いにくいデザイン」より「シンプルだが使いやすいデザイン」の方が、圧倒的に価値が高いと考えています。
4. 短命なデザインになる
トレンドは移り変わります。トレンドに乗りすぎたデザインは、2〜3年で古臭く見えてしまいます。
WEBサイトのリニューアルには多大なコストがかかります。
頻繁にリニューアルできない企業にとって、流行に左右されにくい「長く使えるデザイン」の方が価値があります。
私がデザインするとき、意識しているのは「3年後に見ても古く感じないデザイン」という事!
適度にトレンドを取り入れつつ、普遍的な美しさと機能性を重視する。そのバランスが重要なんです!
まとめ
いかがでしたか?
今回はデザイントレンドとの正しい向き合い方について解説してきました。
トレンドとの付き合い方は、デザイナーとしての成熟度を示すバロメーターです。
駆け出しの頃は「トレンドを使えばかっこいいデザインになる」と単純に考えがちです。しかし経験を積むにつれ、「トレンドを知っているが、あえて使わない」という判断ができるようになります。これこそが、プロフェッショナルの証だと私は思います。
私が大切にしているのは、「トレンドは手段であって目的ではない」という考え方です。最新の表現技法を知識として蓄え、それをクライアントの課題解決という目的のために適切に使う。時には使わない勇気を持つ!この判断を的確にできるデザイナーでありたいと思っています。お互い頑張りましょう!!
弊社BOPコミュニケーションズでは、Web広告の配信・運用を承っております。
・売上を伸ばすためにWeb広告を活用してみたい。
・自社で広告配信をしているが、手探り状態なので効率を上げたい。
・広告の運用をプロに任せて、よりビジネスを大きくしていきたい。
そんな場合は、お気軽にご相談ください!
★フォームからすぐにお問い合わせしたい場合はこちら↓