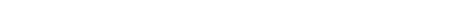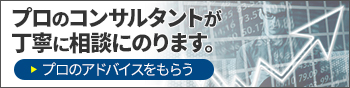2025/05/01
企業が顧客満足度やロイヤルティを測定するうえで、世界中で広く使われている指標として、「NPS(Net Promoter Score)」というものがあります。
このNPS(ネット・プロモーター・スコア)は、BtoC・BtoBを問わず導入されており、その簡潔な設計と実用性から、多くの企業がマーケティングやCX(顧客体験)改善に活用されています。
今回は、NPSの意味や測定方法、スコアの読み解き方、そして混同されやすいBLS(Brand Loyalty Score)との違いなどをご紹介します。
NPSとは?
NPSとは、顧客に対して「この商品/サービスを友人や同僚にすすめたいと思いますか?」というシンプルな質問を行い、0〜10点で評価してもらうことで、顧客の推奨意向(=ロイヤルティ)を可視化する指標です。
多くの企業がNPSをKPIに取り入れており、カスタマーサクセスやマーケティング施策の改善材料としても使われています。
NPSでの回答分類とスコアの計算方法
NPSでは、0〜10点で回答されたスコアを以下のように分類します。
・9〜10点をつけた人は「推奨者(Promoters)」とされ、企業や商品を積極的に他人にすすめてくれる存在です。
・7〜8点の人は「中立者(Passives)」で、満足はしているものの、特に他人にすすめるほどではない層です。
・0〜6点の人は「批判者(Detractors)」で、商品に不満を持ち、離脱やネガティブな口コミを広げるリスクがあるとされます。
この分類に基づいて、NPSは以下のように計算されます。
NPS = 推奨者の割合(%) − 批判者の割合(%)
例えば、アンケート回答者のうち60%が推奨者、20%が批判者だった場合、NPSは +40 となります。
ここで注意すべき点があります。
NPSのスコアは、元の評価が0〜10点であっても、最終的なスコアは「-100〜+100」の範囲で表されます。
これは、全員が批判者であれば-100、全員が推奨者であれば+100となる為です。
つまり、「10点満点中◯点」というスコアではなく、「顧客全体のロイヤルティバランスを示すパーセンテージスコア」ということです。
NPSが活用される場面
NPSは、特に次のような場面で活用されます。
・新商品の評価やフィードバックの収集
・顧客体験(CX)改善の指標として活用
・定点的なブランドの健康状態(ブランドヘルス)の可視化
・支店・部署・サービスごとの比較分析
特に「改善ポイントが明確に見える」点がNPSの強みであり、スコアを定点観測することで顧客との関係性の変化を追うことができます。
NPSとBLSの違いとは?
混同されやすい指標として、「BLS(Brand Loyalty Score:ブランド・ロイヤルティ・スコア)」があります。
NPSとBLSの違いを簡単に説明すると、以下のようになります。
・NPS は「このブランドをすすめたいか?」という推奨意向にフォーカスしています。
・BLS は「今後も購入したい・使い続けたい」という継続意向やブランドへの忠誠心を含めて評価する指標です。
また、BLSはアンケートのスコアだけでなく、実際の購買履歴や接触頻度などのデータも活用してスコア化するケースが多く、より実態に即したロイヤルティ分析が可能です。
目的や使いたい場面によって、「推奨意向」を見たいならNPS、「実際の継続度合い」を知りたいならBLSと使い分けるのが効果的です。
よくある誤解と補足
NPSは「平均点」ではない
→ 顧客の声を単純な平均でなく、「すすめたい人がどれだけいるか、避けたい人がどれだけいるか」に注目するのが特徴です。
中立者はスコアに影響しないが、母数には含まれる
→ 推奨者と批判者の割合差だけで計算されるため、特に批判者が多いとマイナスになることも。
よくある質問(FAQ)
Q1. NPSのスコアは何点以上なら「良い」と言えますか?
A. 業界や市場によって基準は異なりますが、一般的に「0以上」であればポジティブな評価とされます。
+30以上になるとロイヤルティが高いと見なされ、+50以上は優れた水準といえるでしょう。
Q2. NPSの調査はどれくらいの頻度で行うべきですか?
A. 半年に1回、または四半期に1回の定点調査が推奨されます。
キャンペーン実施後や新サービス導入後などのタイミングで実施すると、施策の影響を把握しやすくなります。
Q3. BtoBでもNPSは活用できますか?
A. はい、むしろBtoBの方が有効な場合もあります。
意思決定者が明確で、定期的な接点があるため、関係性の質を定量的に測る手段として活用されています。
Q4. NPSスコアを上げるには何をすれば良いですか?
A. 推奨者を増やす取り組み(CX向上・サポート改善)と、批判者を減らす改善施策(不満の原因特定と解消)の両方が必要です。
アンケートに「自由記述欄」を設けると、具体的な改善点が見えてきます。
Q5. BLS(ブランド・ロイヤルティ・スコア)との併用は可能ですか?
A. はい、併用することで「推奨意向(NPS)」と「継続意向・実行傾向(BLS)」の両面からロイヤルティを把握できます。
より深い顧客理解を求める企業では、両指標をセットで活用するケースが増えています。
Q6. NPS調査で中立者(7〜8点)の扱いはどうするべき?
A. スコア計算には含まれませんが、フィードバック分析の対象として重要です。
中立者はポジティブにもネガティブにも転じる可能性が高いため、丁寧なフォローが必要です。
まとめ
今回は、NPS(Net Promoter Score)について、ご紹介しました。
NPSは、シンプルな質問ひとつで、顧客のロイヤルティを測定できる有力な指標です。
特に、推奨意向をベースにした評価ができる点は、他の指標とは異なる強みです。
ただし、0〜10点で回答する仕組みに慣れていると「スコアもその中で出る」と誤解されがちです。
NPSスコアは −100〜+100の範囲であることを正しく理解したうえで、継続的な分析・改善に役立てていきましょう。
弊社BOPコミュニケーションズでは、Web広告の配信・運用を承っております。
・売上を伸ばすためにWeb広告を活用してみたい。
・自社で広告配信をしているが、手探り状態なので効率を上げたい。
・広告の運用をプロに任せて、よりビジネスを大きくしていきたい。
そんな場合は、お気軽にご相談ください!
★フォームからすぐにお問い合わせしたい場合はこちら↓